アンゴルモア=モンゴル説を検証する その1 ― 2016/07/20 00:03

1961年に出版されたエドガー・レオニのノストラダムス研究書"Nostradamus: Life and Literature"(ノストラダムス、伝記と文学)の表紙には10-72の予言詩の英訳とともにヨーロッパの地図を背景に東洋人風パイロットが奇妙な戦闘機に乗って攻めてくる絵とともに「????」マークが並んでいる。図柄は当時から見た遠未来を予感させる仕上げになっている。その英訳はこうなっている。
The year 1999, seventh month,
From the sky will come a great King of Terror:
To bring back to life the great King of the Mongols・・・
1999年、七番目の月
空から恐怖の大王が到来するだろう
モンゴル人の大王を甦らせるために
From the sky will come a great King of Terror:
To bring back to life the great King of the Mongols・・・
1999年、七番目の月
空から恐怖の大王が到来するだろう
モンゴル人の大王を甦らせるために
モンゴル人と英訳されている原句はAngolmoisなのだが、レオニは語釈のなかで「アングレーム地方ではなくおそらく古いフランス語のMongoloisモンゴル人のアナグラム」と述べている。「アナグラムはRoi des Mongoloisとした場合に生じる余分な音節を避ける役割がある」ともいっている。そもそもノストラダムスの予言集では、5-54にタタールTartarieという句があるが直接モンゴルに言及されたことはない。その後モンゴル説は1970年に出版されたコリン・ウィルソンの"The occult"に引き継がれる。
アンゴルモワの大王とは、殆ど確実にジンギス汗のことである。「Angolmois」というのもノストラダムスのアナグラムの一つで、綴りの順序を変えると、「Mongolians」蒙古人となる。ひょっとしたら彼はこのスタンザで「黄禍」にたいして警告しているのかもしれない。
コリン・ウィルソン『オカルト 上巻』中村保男訳,新潮社,1973,281頁
コリン・ウィルソン『オカルト 上巻』中村保男訳,新潮社,1973,281頁
エリカ・チータムの初期版"The Prophecies of Nostradamus"1973では、10-72の三行目はレオニに倣って"He will bring back to life the great king of Mongols."と英訳された。日本では金森誠也氏が1981年の『洪水大予言』216頁でチータムを参照して「モンゴルの大王をよみがえらせ」と訳している。ただし、1982年の『惑星グランド・クロス』178頁では「モンゴル?」の章でチータムの注釈を引用し、フェニックス・ノア氏のアングルモア=モンゴルとの断定に懐疑的な姿勢を見せつつも「まっこうから珍説としてしりぞけることはできない」と含みを持たせている。
チャールズ・バーリッツの1981年の"Doomsday, 1999 A.D"にもモンゴルへの言及がある。
この予言詩は現代の解釈者によって、原爆投下、放浪惑星の衝突、あるいはたぶん中国人による(アングルモアを"モンゴル"の暗号読みとして)大空襲などと、諸説ふんぷんだ。
チャールズ・バーリッツ『一九九九年運命の日』南山宏訳,二見書房,1981,52頁
チャールズ・バーリッツ『一九九九年運命の日』南山宏訳,二見書房,1981,52頁
日本では五島勉氏の1979年『ノストラダムスの大予言Ⅱ』138頁や193頁でこの説が紹介されて以来モンゴル説が市民権を得てメジャーとなっていった。このようにアンゴルモア=モンゴル説はレオニが発信元で、,英語圏の注釈者を通じて日本に導入されていった解釈であることがわかる。しかしそもそもレオニはなぜ唐突にモンゴル説を打ち出したのだろう。少し前に入手した、戦時中米国のインディアナポリスで出版されたノストラダムス本にその鍵があると思われる。
アンゴルモア=モンゴル説を検証する その2 ― 2016/07/20 00:14
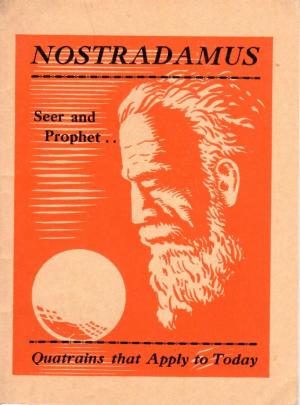
その本は1941年に出版された"Nostradamus Seer and Prophet.. Quatrains that Apply to Today"(ノストラダムス、予見者で予言者、今日に当てはまる四行詩群)で著者名はない。わずか48頁の小冊子である。レオニによると「プロナチ(親ナチ)のプロパガンダ・パンフレットでNorabの本に基づいている」という。文献リストにも載っているためレオニがこの本を参照したのは間違いない。同書42頁では1999年について言及が見られる。
1947年以降は、ノストラダムスはまとまった年を通り越して1999年の予言を続けている。彼はその年のことを非常にはっきりと記述している。
恐ろしい王が空から降りてくる。彼はギリシャ語やラテン語とは源流を異なる見知らぬ言語を話す。彼はひどい破壊をもたらす武器を巧みに操ることができる。トナカイが彼とともにいるだろう。
注釈者たちはこの「トナカイ」がシベリア北部のとある民族あるいはモンゴルの象徴と信じている。彼らはチンギス・ハンのもとで11世紀の侵略するモンゴル人たちの精神力と力強さに近づくほどの大きな民族の復活を経験するのかもしれない。
恐ろしい王が空から降りてくる。彼はギリシャ語やラテン語とは源流を異なる見知らぬ言語を話す。彼はひどい破壊をもたらす武器を巧みに操ることができる。トナカイが彼とともにいるだろう。
注釈者たちはこの「トナカイ」がシベリア北部のとある民族あるいはモンゴルの象徴と信じている。彼らはチンギス・ハンのもとで11世紀の侵略するモンゴル人たちの精神力と力強さに近づくほどの大きな民族の復活を経験するのかもしれない。
この部分は黒沼健氏の「七十世紀の大予言」(黒沼健『謎と怪奇物語』新潮社、1957年)の60頁に非常によく似ている。その下敷きになったヘンリー・ジェームズ・フォアマンの『予言物語』186頁にはこう書かれている。
彼はラテン語ではない見知らぬ言語を話す軍隊を引き連れて来る。彼らは恐ろしい武器だけでなく、トナカイをも引き連れている。アジア人のヨーロッパ侵略は常に直面している。今でもその多くがトナカイを引き連れているシベリア北部の民族が、ゆっくりとヨーロッパに対する新しい未来の脅威を形づくっている。
最初にこれを読んで疑問に思ったのがなぜ1999年の詩とトナカイが関係しているのかである。その解釈のルーツはピエール・ピオッブの著作"Le secret de Nostradamus"142頁にある。
Par langues estranges seront tendues tentes,
Fleuves, dards, rennes, terre et mer trembleront(I.20).
Fleuves, dards, rennes, terre et mer trembleront(I.20).
ちなみに1555年版予言集では1-20の3,4行目の原文はこうなっている。
Par langues estranges seront tendues tentes,
Fluues,dards Renes,terre & mer tremblement.
Par langues estranges seront tendues tentes,
Fluues,dards Renes,terre & mer tremblement.
RenesのRは1555年、1557年、1568年版ではすべて大文字となっている。ところがピオッブの底本である1668年アムステルダムで出版されたジャン・ジャンソン版ではrenesと小文字である。さらにピオッブがこれをrennes(トナカイ)に書き直したことでシベリア北部の民族の象徴という解釈が生まれ、それを拡大解釈することでモンゴルが導かれたのである。本来結びつくことのない1999年の詩とモンゴル、ここをロジカルに関連づけするテクニックとしてレオニがアナグラムに目を付けたのでないか。
ちなみにレオニの英訳では
Tents will be pitched by those of foreign tongues,
Rivers, darts at Rennes trembling of land and sea.
異国の言葉の人々によりテントが張られるだろう
レンヌで川、投げ矢、大地と海の震え
Nostradamus : Life and Literature, p137
Rivers, darts at Rennes trembling of land and sea.
異国の言葉の人々によりテントが張られるだろう
レンヌで川、投げ矢、大地と海の震え
Nostradamus : Life and Literature, p137
とあり、Renesを文字通り地名として受け取っているがレンヌという地名は文脈上唐突な感じがしないでもない。ピーター・ラメジャラの英訳には発音に着眼したブランダムールの校訂d'arenesに従ってsandy rivers(砂だらけの川)も併記されている。1999年の詩の解釈とモンゴルを結び付けるには1-20の詩をピオッブのようにrennes(トナカイ)と読んで10-72の詩の状景を補完し、1941年の解釈書のなかでモンゴルが引き出されて1999年のヨーロッパへの侵略者の幻影が生まれたと考えられる。
レオニが草稿を作成した1950年といえば戦争が終結してわずか5年しか経っていない。レオニがAngolmoisにモンゴルのアナグラムを読み取ろうとしたのは第二次世界大戦の生々しい記憶が完全に払拭されていない時代心象によるものかもしれない。

最近のコメント