ノストラダムス書誌学者ショマラの本 ― 2008/03/01 23:59
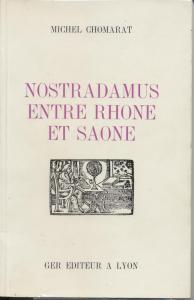
ノストラダムスの書誌について論じるとき、ミシェル・ショマラの研究成果を外すことはありえない。ショマラの書誌研究の集大成は、1989年に刊行された"Bibliographie Nostradamus XVIe-XVIIe-XVIIIe siecles"(ノストラダムス文献書誌16-17-18世紀)にまとめられている。現在では、これを基礎とした新たな書誌研究も発表されている。宮下史朗氏の「16世紀出版文化の中のノストラダムス」(『ノストラダムスとルネサンス』所載)のように、ノストラダムス本の分類では、この本の略語[BN]で表記することも多い。書誌を調べていくと、それなりに面白くなり、どんどん深みにはまってしまう。そんな魔力さえも感じる。
ショマラは在野の研究者で、若いときリヨンの印刷業に見習いとして飛び込んだ。リヨンの古い書物に接するうちにノストラダムスと出会い、以後コツコツと文献を集めていった。リヨン市立図書館のショマラ文書庫には世界有数のノストラダムスコレクションが保管されている。その一部は日本のテレビ番組でも紹介されたことがある。ショマラの最初の研究は1971年の"Nostradamus entre Rhone et Saone"(ローヌとソーヌの間のノストラダムス)で世に出ている。当時23歳。先行研究の乏しいなかで、自らの手で探究した書誌研究が素晴らしい。日本で、かの『ノストラダムスの大予言』がベストセラーになる以前の話である。
その後も『ノストラダムスのリヨン書誌』で、ノストラダムス本の整理をしたり一族の手稿を調べ上げた。ショマラは自ら出版社を経営しており、ノストラダムス予言集のボノム版、ローヌ版(海賊版)、リゴー版のファクシミリ本を印刷、研究の基礎となるマテリアルを提供している。書誌研究を踏まえた学術的な論考もいくつか発表している。まさに現代研究の先駆けといっても過言ではない。昨今のグループによって白熱するノストラダムス文献の渉猟について、ショマラ自身どう考えているのだろうか。
ショマラは在野の研究者で、若いときリヨンの印刷業に見習いとして飛び込んだ。リヨンの古い書物に接するうちにノストラダムスと出会い、以後コツコツと文献を集めていった。リヨン市立図書館のショマラ文書庫には世界有数のノストラダムスコレクションが保管されている。その一部は日本のテレビ番組でも紹介されたことがある。ショマラの最初の研究は1971年の"Nostradamus entre Rhone et Saone"(ローヌとソーヌの間のノストラダムス)で世に出ている。当時23歳。先行研究の乏しいなかで、自らの手で探究した書誌研究が素晴らしい。日本で、かの『ノストラダムスの大予言』がベストセラーになる以前の話である。
その後も『ノストラダムスのリヨン書誌』で、ノストラダムス本の整理をしたり一族の手稿を調べ上げた。ショマラは自ら出版社を経営しており、ノストラダムス予言集のボノム版、ローヌ版(海賊版)、リゴー版のファクシミリ本を印刷、研究の基礎となるマテリアルを提供している。書誌研究を踏まえた学術的な論考もいくつか発表している。まさに現代研究の先駆けといっても過言ではない。昨今のグループによって白熱するノストラダムス文献の渉猟について、ショマラ自身どう考えているのだろうか。
綺想の表象学―エンブレムへの招待 ― 2008/03/02 23:50
http://bookweb.kinokuniya.co.jp/htm/4756607985.html
昨日散髪の帰りに久し振りに本屋に立ち寄った。人文書コーナーの棚を見ると、伊藤博明 綺想の表象学―エンブレムへの招待 ありな書房 2007年 が置いてあった。エンブレムについては『ノストラダムスとルネサンス』の「四行詩について」で読んだ記憶がある。手にとってみると542頁もの大著であるが中には図版が豊富に取り込まれており、エンブレムを眺めているだけでも面白い。第1章にはオラポロンの『ヒエログリフ集』がどうのようにルネサンス期に流布したか解説されている。ノストラダムスが最初に執筆した作品はオラポロンを詩の形式で訳出したものであった。当時印刷されなかったが手稿がフランスの国立図書館に保管されている。
1968年にはピール・ロレにより手稿を校正したものが初めて刊行された。手元にあるのは標本ナンバー901番である。そのなかにはところどころ木版画が挿入されおり、詩文のイメージ化が図られている。『綺想の表象学』の序文にもあるように、まさに「詩は絵のごとく」である。エンブレムとはもともと宗教上の道徳を説くもので、図像は言葉により解き明かされる。通常は表題、図像、エピグラム(四行詩のケースも見られる)から構成される。広く文学者や知識人により用いられていた。細川哲士氏によると、やがて奇妙な図柄に謎の言葉が添えられ図像の象徴化が進んでいった。エピグラムがテクストととして独立した四行詩として読まれるようになる。
ノストラダムスの予言でいえば、マテリアルは置いておいて、頭のなかにある予言イメージ、つまりエンブレムに相当するものを四行詩をいう流行の形態で記していった。これらがまとまった形でサンチュリ(百詩篇)が出来上がったものと考えられる。本当にそうした裏付けが取れるかどうか、この本が参考になればと思う。
昨日散髪の帰りに久し振りに本屋に立ち寄った。人文書コーナーの棚を見ると、伊藤博明 綺想の表象学―エンブレムへの招待 ありな書房 2007年 が置いてあった。エンブレムについては『ノストラダムスとルネサンス』の「四行詩について」で読んだ記憶がある。手にとってみると542頁もの大著であるが中には図版が豊富に取り込まれており、エンブレムを眺めているだけでも面白い。第1章にはオラポロンの『ヒエログリフ集』がどうのようにルネサンス期に流布したか解説されている。ノストラダムスが最初に執筆した作品はオラポロンを詩の形式で訳出したものであった。当時印刷されなかったが手稿がフランスの国立図書館に保管されている。
1968年にはピール・ロレにより手稿を校正したものが初めて刊行された。手元にあるのは標本ナンバー901番である。そのなかにはところどころ木版画が挿入されおり、詩文のイメージ化が図られている。『綺想の表象学』の序文にもあるように、まさに「詩は絵のごとく」である。エンブレムとはもともと宗教上の道徳を説くもので、図像は言葉により解き明かされる。通常は表題、図像、エピグラム(四行詩のケースも見られる)から構成される。広く文学者や知識人により用いられていた。細川哲士氏によると、やがて奇妙な図柄に謎の言葉が添えられ図像の象徴化が進んでいった。エピグラムがテクストととして独立した四行詩として読まれるようになる。
ノストラダムスの予言でいえば、マテリアルは置いておいて、頭のなかにある予言イメージ、つまりエンブレムに相当するものを四行詩をいう流行の形態で記していった。これらがまとまった形でサンチュリ(百詩篇)が出来上がったものと考えられる。本当にそうした裏付けが取れるかどうか、この本が参考になればと思う。
A級順位戦最終局、羽生が名人挑戦を決めた ― 2008/03/04 00:17
http://mainichi.jp/enta/shougi/index.html
本日というか、もう昨日になるが、将棋界の一番長い日A級順位戦の最終局が行われた。有料中継を見れないのではっきりしないがまだ終わっていない対局もあるだろう。毎日のサイトでは速報で羽生のニュースを流した。最終局の見どころは二つである。久保、佐藤のどちらがA級から降級となるか、もう一つは今期成績がガタガタだった谷川が今期一番の大勝負となる対羽生戦で、まだまだ力のあるところを示せるかだ。羽生の名人戦挑戦者はほぼ間違いないところだが谷川は来期の順位戦に向けての信用というものがある。
ここで踏ん張れれば自信につながり来期の巻き返しのはずみとなるはずだ。しかし結果は無残にも短手数での敗戦。10時半には終了していたというのはいただけない。谷川の順位は7位で確定。来期はとてつもなく厳しい戦いになると予想される。今月号の将棋世界を読むと、降級のピンチを迎えたプレッシャーのかかる一番で、いかに手厚く指せるかで勝負強さが違ってくる。佐藤はそれを実践していた。対三浦戦を見ると、谷川はこれまでのように強気の攻めに活路を見出そうとしていた。この棋風も皆に覚えられてしまったのかもしれない。
中原が矢倉中心の手厚い将棋から相掛りや横歩取りのような軽快な将棋に棋風改造したように、谷川も生き残るためには何かしらの改造が必要ではないか。同世代だけにA級で孤軍奮闘頑張ってほしいものである。
本日というか、もう昨日になるが、将棋界の一番長い日A級順位戦の最終局が行われた。有料中継を見れないのではっきりしないがまだ終わっていない対局もあるだろう。毎日のサイトでは速報で羽生のニュースを流した。最終局の見どころは二つである。久保、佐藤のどちらがA級から降級となるか、もう一つは今期成績がガタガタだった谷川が今期一番の大勝負となる対羽生戦で、まだまだ力のあるところを示せるかだ。羽生の名人戦挑戦者はほぼ間違いないところだが谷川は来期の順位戦に向けての信用というものがある。
ここで踏ん張れれば自信につながり来期の巻き返しのはずみとなるはずだ。しかし結果は無残にも短手数での敗戦。10時半には終了していたというのはいただけない。谷川の順位は7位で確定。来期はとてつもなく厳しい戦いになると予想される。今月号の将棋世界を読むと、降級のピンチを迎えたプレッシャーのかかる一番で、いかに手厚く指せるかで勝負強さが違ってくる。佐藤はそれを実践していた。対三浦戦を見ると、谷川はこれまでのように強気の攻めに活路を見出そうとしていた。この棋風も皆に覚えられてしまったのかもしれない。
中原が矢倉中心の手厚い将棋から相掛りや横歩取りのような軽快な将棋に棋風改造したように、谷川も生き残るためには何かしらの改造が必要ではないか。同世代だけにA級で孤軍奮闘頑張ってほしいものである。
ジャック・アルブロンの論文(刊行本)が届いた ― 2008/03/04 23:00
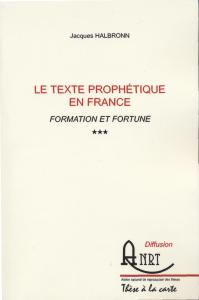
http://www.propheties.it/halbronn/index.html
以前アルブロンの論文の重たい電子データがアップされた話を紹介したが、その刊行本がようやく手元に届いた。総ページ数が1356頁と膨大なのでどんな形の本だろうと思っていたら三分冊になっている。価格は122Euros。アップされたpdfと比べてみると、もちろん内容は同じなのだが活字の組み直しをしているらしくタイトル字のレイアウトなどが微妙に異なる。pdfファイルは冒頭に論文のレジメやキーワード、著者のサインなどが見られるが刊行本は謝辞から始まっている。すなわちpdfのほうは論文のオリジナルで、刊行本のほうは「論文複製の国立アトリエ」(ANRT)でリプロダクションされたものとわかる。複製本は字は小さいがくっきりしているのでパソコンで見るより読みやすい。
改めて頁をめくってみると、本は三部構成からなる。第一部「フランス教会の予言主義、プログラム」は12章からなり時代ごと予言に関わるテーマを扱っている。第二部「デルフォイの予言主義、集成」は13章から21章まで、ミラビリス・リベルやムーの永続的予言など個別の予言書を集めている。第三部「サンチュリの予言主義、神託」は22章から30章が当てられ、主にノストラダムスの予言集や暦書について論じている。最後に結論と付録(一次ソースと二次ソースの参考文献と予言書の表紙のコピー)がくるが、それでも90頁ほどのボリュームがある。拾い読みをしてみると、ノストラダムスについても実に様々なテーマを扱っており、まさに宝の山である。
その一部は「ジャック・アルブロンの論文」(http://ramkat.free.fr/thalb.html)で紹介されているが、サマリーの内容は完結していない。そうこうするうちにマリオのサイトで全てが公開されたわけだ。なにはともあれアルブロンの博覧強記ぶりには、ただただ驚きの念を抱くばかりである。
以前アルブロンの論文の重たい電子データがアップされた話を紹介したが、その刊行本がようやく手元に届いた。総ページ数が1356頁と膨大なのでどんな形の本だろうと思っていたら三分冊になっている。価格は122Euros。アップされたpdfと比べてみると、もちろん内容は同じなのだが活字の組み直しをしているらしくタイトル字のレイアウトなどが微妙に異なる。pdfファイルは冒頭に論文のレジメやキーワード、著者のサインなどが見られるが刊行本は謝辞から始まっている。すなわちpdfのほうは論文のオリジナルで、刊行本のほうは「論文複製の国立アトリエ」(ANRT)でリプロダクションされたものとわかる。複製本は字は小さいがくっきりしているのでパソコンで見るより読みやすい。
改めて頁をめくってみると、本は三部構成からなる。第一部「フランス教会の予言主義、プログラム」は12章からなり時代ごと予言に関わるテーマを扱っている。第二部「デルフォイの予言主義、集成」は13章から21章まで、ミラビリス・リベルやムーの永続的予言など個別の予言書を集めている。第三部「サンチュリの予言主義、神託」は22章から30章が当てられ、主にノストラダムスの予言集や暦書について論じている。最後に結論と付録(一次ソースと二次ソースの参考文献と予言書の表紙のコピー)がくるが、それでも90頁ほどのボリュームがある。拾い読みをしてみると、ノストラダムスについても実に様々なテーマを扱っており、まさに宝の山である。
その一部は「ジャック・アルブロンの論文」(http://ramkat.free.fr/thalb.html)で紹介されているが、サマリーの内容は完結していない。そうこうするうちにマリオのサイトで全てが公開されたわけだ。なにはともあれアルブロンの博覧強記ぶりには、ただただ驚きの念を抱くばかりである。
順位戦の各クラスも大詰めを迎えた ― 2008/03/06 01:08
http://www.asahi.com/shougi/
昨日はC級2組の最終局が終了し、昇級者と降級者が決まった。最近のC級はず抜けた若手がいないので昇級ラインが下がっている。大人数に起因する1敗頭ハネというのはなさそうだ。先ごろA級順位戦が終了し、結局陥落は久保八段となった。佐藤二冠としてはタイトルホルダーの陥落という不名誉はなんとか自力で回避した。さすがにここ一番の底力は超一流棋士といったところ。佐藤が勝った瞬間に久保の陥落が決まったのだが、久保は千日手指し直しの末に敗れた。指し直しのときにはすでに結果を知ってしまったのだろうか。だとしたら、心情的にはやむを得ない。
久保はA級に連続5期いたが、なかなか挑戦者争いに絡むことができなかった。今期は王将戦の挑戦者になるなど決して調子が悪いわけではない。それでも勝つのが難しいのがA級というトップクラスなのだ。久保の今の力をもってすればB1で昇級候補とみるのは衆目の一致するところ。精神面を立て直しての捲土重来を切に願う。今期より朝日も名人戦を紙面に掲載している。同時にインターネット上でも速報を流している。毎日と朝日の将棋のサイトを比較すると間違いなく朝日の情報のほうが充実している。結果のみでなく千日手指し直しも一つのトピックとして報じられていた。
ダブル観戦記にしてもいい意味での競争といえると思うのだが、やはり不自然な感じは否めない。実際問題、現場で不都合とかないのだろうか。いつまでこのスタイルが続くのか、少々疑問に思う。
昨日はC級2組の最終局が終了し、昇級者と降級者が決まった。最近のC級はず抜けた若手がいないので昇級ラインが下がっている。大人数に起因する1敗頭ハネというのはなさそうだ。先ごろA級順位戦が終了し、結局陥落は久保八段となった。佐藤二冠としてはタイトルホルダーの陥落という不名誉はなんとか自力で回避した。さすがにここ一番の底力は超一流棋士といったところ。佐藤が勝った瞬間に久保の陥落が決まったのだが、久保は千日手指し直しの末に敗れた。指し直しのときにはすでに結果を知ってしまったのだろうか。だとしたら、心情的にはやむを得ない。
久保はA級に連続5期いたが、なかなか挑戦者争いに絡むことができなかった。今期は王将戦の挑戦者になるなど決して調子が悪いわけではない。それでも勝つのが難しいのがA級というトップクラスなのだ。久保の今の力をもってすればB1で昇級候補とみるのは衆目の一致するところ。精神面を立て直しての捲土重来を切に願う。今期より朝日も名人戦を紙面に掲載している。同時にインターネット上でも速報を流している。毎日と朝日の将棋のサイトを比較すると間違いなく朝日の情報のほうが充実している。結果のみでなく千日手指し直しも一つのトピックとして報じられていた。
ダブル観戦記にしてもいい意味での競争といえると思うのだが、やはり不自然な感じは否めない。実際問題、現場で不都合とかないのだろうか。いつまでこのスタイルが続くのか、少々疑問に思う。

最近のコメント